|
|
|
| 10/11 | |
|
薬草講座:武居末子先生 |
|
 |
 |
|
食事の後は、身近な薬草の活用法という事で講義をして頂きました。 初めて医薬が作られたのは、西暦150〜219年の中国の張仲景によるそうで、傷寒難病論という著書も残っているそうです。 薬用植物は本来すべて毒草で、薬効の高い薬草は300種ほどあり、県内で自生するものは120種ほどあるそうです。 生薬で一番多様なものは植物で、全草・根・枝・葉などがもちいられるとか。
まずは、薬草と類似の毒草の判別、採取時期・利用加工法、用いる人の状態等の正しい知識が必要になってくるそうです。 |
|
 |
 |
|
身近な薬草としては、甘草、アキカラマツ、ゲンノショウコ、オケラ、センブリ、ドクダミ、オオバコ、 ハコベ、イカリソウ、キンミズヒキ、ヨモギ、ショウブ、アカザ、シソ、 樹皮を使うものとしてキハダ、ホウノキ、実を使うものとしてクサボケ、キカラスウリ等を紹介して頂きました。
桑は樹木全てが薬となるそうです。 |
|
 |
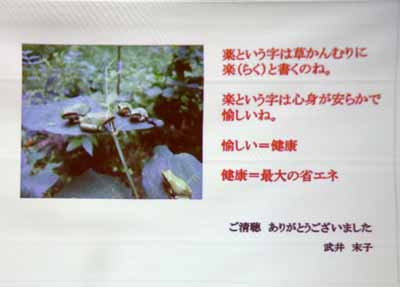 |
|
先生曰く、薬は草+楽。 楽は健康。 健康は最大の省エネとなるそうです。 |
|
| 寺社一覧へ | 目次へ・・・・次ページ・・・・戻る |
|
|
|